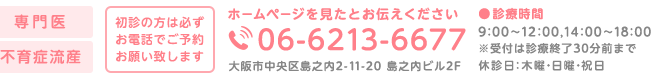内科疾患合併症妊娠
 お母さんが高血圧、糖尿病、自己免疫疾患、心疾患など内科疾患を持って妊娠する場合、内科疾患合併症妊娠となります。内科合併症妊娠もある意味で不育症といえます。お母さんが作る子宮内環境がお母さんの病気によって悪くなるとき、赤ちゃんの発育が妨げられることがあるからです。
お母さんが高血圧、糖尿病、自己免疫疾患、心疾患など内科疾患を持って妊娠する場合、内科疾患合併症妊娠となります。内科合併症妊娠もある意味で不育症といえます。お母さんが作る子宮内環境がお母さんの病気によって悪くなるとき、赤ちゃんの発育が妨げられることがあるからです。
私は、大阪府立母子保健総合医療センター母性内科で27年間、内科合併症妊娠を診てきました。内科合併症妊娠で大切なことは、妊娠中の管理だけでなく、妊娠前からの準備が大切であるということです。分娩後の管理もまた大切です。
例えば、糖尿病合併妊娠では、妊娠前から厳格に血糖コントロールをすることで、赤ちゃんの奇形発生を大幅に減らすことができます。妊娠中の血糖コントロールによって、正常血糖に近づけば近づくほど、生まれてくる赤ちゃんが生まれた時の合併症(低血糖 黄疸巨大児など)が、少ないことも知られています。分娩後はインスリンの必要量の変化が激しいので注意が肝要です。
ここでは、内科合併症の中でも妊娠を考える時極めて重要な、自己免疫疾患についてお話します。
自己免疫疾患に限らず、内科合併症妊娠を扱うときには、妊娠前管理、妊娠中の管理、産褥管理の三つの時期に分けて考えるべきです。また、その場合内科医は、母体の管理だけを優先するのではなく、同時に胎児の状況も把握しなければなりません。
妊娠前管理
自己免疫疾患の多くが、生殖年齢の女性に発症しやすいものであることはよく知られています。自己免疫疾患女性を日常診ている医師は、その女性が結婚しているか否かは別にして、妊娠の可能性があれば、妊娠とその疾患について必ず詳しい説明をしておくべきです。
その説明とは
- その疾患が妊娠、胎児に与える影響
疾患の活動性の程度、腎症合併の有無、高血圧の有無、特異な自己抗体の有無などが妊娠中毒症の発症、胎児の発育に大きな影響を与えます。 - 現在処方している薬が胎児に与える影響
妊娠初期は胎児の器官形成期にあたります。とくに妊娠12週までの薬の使用については注意が必要です。妊娠に気づいた時はすでに10週、12週を過ぎていたということは、決してまれではありません。 - 妊娠、分娩がその疾患に与える影響
妊娠中に寛解しやすい疾患もあれば、悪化しやすいものもあります。分娩後は、ほとんどの疾患が悪化しやすいのです。
これらの説明をした上で、女性が妊娠を希望すれば対処の方法を考えねばなりません。しかし、日頃から自分が診ている自己免疫疾患をもつ女性が、妊娠について何の説明も受けず、いきなり妊娠が成立し、不測の事態が起こったときは、医師がその責任を取る時代になっていることを覚悟しなければならないと思います。
妊娠中の管理
妊娠中の管理の要点は、母体管理だけに眼を向けず、常にその母体が作っている子宮内環境に置かれている胎児にも眼を向けることです。
妊娠12週までは、催奇形性の可能性の強い薬剤は避けねばならなりません。原則です。しかし、薬を使うことによって胎児にとっての子宮内環境がより改善するのであれば、積極的に安全な薬を使用します。たとえば母体がループスアンチコアグラントを保有しているとき、胎盤梗塞を防ぐ目的で妊娠初期からヘパリンを使います。また母体が高値の抗SS-A抗体を保有しているとき、胎児の先天性完全房室ブロックを防ぐ目的で、妊娠13週から副腎皮質ホルモンを使います。このヘパリンと副腎皮質ホルモンを使用する妊娠中の治療の目的は、胎児にとっての子宮内環境の改善であり、胎児内科治療そのものであります。
妊娠中に疾患の活動性を抑えるために、副腎皮質ホルモンを増量することをためらってはいけませんが、この治療も見方を変えれば、母体の血流が形作る子宮内環境を改善するためのものだと言えます。自己免疫疾患に限らず、妊娠中の内科合併症治療の要点は、母体治療が胎児にとっての子宮内環境を改善する胎児内科治療に通じているということなのです。
自己免疫疾患に腎症、高血圧を合併することはまれではありません。このような場合の妊娠予後は、母体にとっても胎児にとっても不良のことが多いのです。微小血管変化がその病変の主たるものである自己免疫疾患において、そのほとんどを血管が占め、血流が重要である胎盤に血管変化がないはずはありません。自己免疫疾患合併妊娠において、いかにして妊娠中毒症の発症を抑えて胎盤血流を正常に近づけるかを模索する必要があります。
産褥管理
自己免疫疾患は、そのほとんどが分娩後に活動性を増します。この事と母乳の問題を考えながら、注意深く産褥管理を行わなければなりません。
副腎皮質ホルモンのうちプレドニゾロンならば、20mgまでは母乳を与えても問題ありません。
分娩後に疾患の活動性が増す前から副腎皮質ホルモンを増量するか、それとも臨床的に活動性が増してから副腎皮質ホルモンを増量するのか、どちらが良いか結論は出ていません。
別の薬剤を使う時、母乳を優先するのか、原病の治療を優先するのか、母親と慎重に相談しながら決定しなければいけません。
慢性関節リウマチを例にとってのべます。
関節リウマチと妊娠
妊娠前管理
関節リウマチの臨床症状は、そのほとんどが妊娠中に軽快か、もしくは不変であり増悪することはありません。しかし、分娩後は再燃する症例が多く、そこでまず育児のサポート体制を整えておくことが大切です。関節機能などの面から、分娩方法も考えておかねばなりません。関節リウマチは、自己免疫疾患であり、いろいろな自己抗体を持つことが多く、妊娠前から抗SS-A抗体、抗リン脂質抗体、甲状腺自己抗体の有無のチェックを怠ってはいけません。
つぎに内服薬の整理が必要です。抗リウマチ薬(DMARDs)については妊娠前から少量のステロイドとNSAIDsに変更することが望ましいです。
妊娠中の管理
妊娠と知らずに抗リウマチ薬をその初期に内服していたとき、妊娠を中断させるはっきりとした根拠はいまのところありません。それぞれの薬における正確な情報をご夫婦に提示することが大切です。
もし妊娠が判明すれば、できればNSAIDsは中止し、ステロイド単独が勧められます。ただし、胎盤を通過しやすいβメサゾン(リンデロン)を使用してはいけません。長期間使用すると、子宮内胎児発育不全の危険性があります。
妊娠中NSAIDsを使用せざるをえない場合でも、妊娠32週以降はその使用を控えるべきだと考えます。胎児動脈管閉鎖を起こすことがあり、子宮内胎児死亡、新生児肺高血圧症の原因となることがあります。大量のアスピリンも胎盤移行し、胎児の血小板機能を低下させるので分娩が想定されれば、その少なくとも一週間前には中止するべきだと考えます。
妊娠中における関節リウマチの活動性の把握には、その臨床症状が第一ですが、検査の指標としてはCRP(炎症所見の検査結果)が有用です。
産褥管理
関節リウマチの多く、その90%が産褥9ヶ月以内に再燃、悪化すると報告されています。多くの症例が分娩前には無投薬か、少量のステロイドのみとなっています。その症例にいつからステロイド、抗リウマチ薬を使用するかは非常に判断が難しいのですが、ステロイドの母乳移行は少なく、抗リウマチ薬の多くは母乳移行があります。
ステロイドを使って母乳を続けるか、断乳して抗リウマチ薬を使うか、このことについて妊娠中から医師と母親が相談し、ある程度のことを決めておくことが大切です。
内科疾患合併症妊娠2
 抗リン脂質抗体症候群 シェーグレン症候群の妊娠合併について
抗リン脂質抗体症候群 シェーグレン症候群の妊娠合併について
胎児治療という立場での母親への薬物療法
自己免疫疾患合併妊娠での大きな問題点は、その妊婦が自己抗体として抗SS-A抗体とループスアンチコアグラントを有しているかです。抗SS-A抗体を有すれば、先天性胎児完全房室ブロックを胎児に発症する可能性があり、またループスアンチコアグラントを有すれば胎児はIUGR(子宮内胎児発育不全)、IUFD(子宮内胎児死亡)に至る可能性が大きいのです。私は、胎児の予後を重大に左右するこの状況を胎児治療という立場で、母親への薬物療法をすることで予防してきました。
Abstract
A severe problem in a pregnant woman with autoimmune disease is that she has or dose not antiSS-A antibody and lupusanticoagulant. If she has antiSS-A antibody, her fetus has some possibility of taking complete A-Vblock. If she has lupusanticoagulant,her fetus has every possibility of IUGR and IUFD. We have prevent these two severe disease in fetus through medicine to a mother.
はじめに
母性内科が誕生して、これまで約30年間、私は母と子の健全なる分娩、出生を目指して模索してきました。ひとつの方向性は、胎児にとっての子宮内環境をいかにして正常に保つかということだと思います。一般の内科医が胎児の立場で医療を考えるということは、はなはだ困難なことのように思えます。ここに一般内科医と一線を画するものがあるといえます。
自己免疫疾患で、その病因の主体をなすものは自己抗体です。ある種の自己抗体は、妊娠中に胎児に対して直接的、間接的に害をもたらします。はっきりと確認されているものに抗SS-A抗体と抗リン脂質抗体であるループスアンチコアグラントの2つがあげられています。この稿ではこれらの自己抗体によって危険にさらされている胎児を母親への薬物療法によって、いかにして子宮内環境を改善し、健全な胎児の出生に寄与するかを述べますが、いずれも世界に先駆けた治療法です。
1 抗リン脂質抗体(ループスアンチコアグラント)による胎盤梗塞を防ぐ試み
a.ループスアンチコアグラントとは
ループスアンチコアグラントとは、抗リン脂質抗体のひとつで、1952年にConleyとHartmannがSLE(全身性エリテマトーデス)患者血中に、血液凝固を阻止する物質が存在することを発見したのが始まりです。リン脂質は血液凝固の場で欠かせない物質で、この抗体は試験管内では、プロトロンビンからトロンビンへの変換を抑制することが知られており、抗凝固的にはたらきます。
しかし、実際に体内では反対に凝固促進的に働き、ループスアンチコアグラントをもった症例は、深部静脈血栓、肺塞栓症、脳梗塞などを起こします。この抗体の存在が知られるようになったのは、最近のことで、しかもこの抗体を持った妊婦が流早産を繰り返すことがわかってから注目され始めました。私は約25年前にループスアンチコアグラントの3症例を日本で初めて報告しました。この3症例はいずれも何度も流産、死産を繰り返した方々です。
ループスアンチコアグラントは、リン脂質に対する自己抗体なので、自己免疫疾患の症例によく見受けられます。特にSLEの症例の約20%に存在すると言われています。抗リン脂質抗体としては、他に抗カルヂオリピン抗体などがあります。これらの抗体を持ち、血小板が減少、いろいろな血栓症の既往があり(そのなかには流死産も含む)はっきりとした自己免疫疾患の症状のない症例を最近では、ひとまとめにして原発性抗リン脂質抗体症候群と呼んでいます。
b.母親へのヘパリン治療の試み
かって25年前には、大阪府立母子保健総合医療センターでは、ループスアンチコアグラントを合併し流死産を繰り返す症例に対して、妊娠初期からの副腎皮質ホルモン療法を行っていました。しかし、全く効果がなく出産に至りませんでした。
流死産の際に、ループスアンチコアグラントの症例に共通する胎盤所見は梗塞です。この点に私たちは注目し、妊娠中の抗凝固療法としてヘパリンを用いることにしました。内科領域での抗凝固療法としてはワーファリンがあります。この薬剤は胎盤を通過し、胎児の出血傾向を助長し、また妊娠初期の使用では、催奇形性の報告もあり使用できません。一方ヘパリンは、胎盤をほとんど通過しないとされており、この治療によってこれまで多数のループスアンチコアグラント陽性の症例が出産に成功しています。
現在では、ループスアンチコアグラントの症例に、妊娠中ヘパリンを使用することは、必須のこととして理解されていますが、当時はその報告がありませんでした。
c.ヘパリンの投与方法について
当時、ヘパリンの投与は、小型携帯ポンプによる精密持続点滴を採用していました。ヘパリン投与は内科領域でも産科領域でも一般的には皮下注射で行っています。
何故持続点滴を採用したか?それは正確な一定のヘパリン血中濃度が大切であると考えたからです。一般的なヘパリンを使用する場合は、1日量約10,000単位を時間400単位(0.4ml)で正確に注入していきます。低分子ヘパリンでは、その半分の量(一日量約5,000単位)を用います。この方法をとっているのは、世界でも大阪府立母子保健総合医療センターのみで画期的な治療法です。
皮下注射に比べてのデメリットは、日常生活の制限、穿刺部からの感染などがあります。しかし、外来通院が可能で、日常生活の制限もわずかであり、数年前から薬剤をポンプに注入する際に、簡易クリーンベンチを使用するようになり、感染は皆無です。
d.低分子ヘパリンの登場
約15年前から日常の臨床で、低分子ヘパリンが使用できるようになりました。通常のヘパリンは、分子量5000-30000と幅が大きいのですが、分画された低分子ヘパリンは4000-6000と分子量が、ほぼ一定でいろんなメリットを持っています。とりわけ産科領域でのメリットは、通常のヘパリンに比べて出血傾向が少ない点です。それは低分子ヘパリンが、血栓形成にキーポイントであるⅩa活性のみを抑制し、止血に重要なⅡa活性をほとんど抑制しないからであり、出血が大きな危険をもたらす妊娠中は、この点で非常に使いやすい薬剤です。
そのほかにも骨粗鬆症を起こしにくい、血小板減少が起こりにくいなどの有用な点があります。しかしながら、コストという点では遥かに高価で、通常ヘパリンの約5倍です。
e.ヘパラン硫酸(オルガラン)の登場
当クリニックでは、ヘパリンあるいは低分子ヘパリンの持続注入はできませんので、現在ではそれと同等の効果のあるオルガランを使っています。オルガランは商品名ヘパラン硫酸といって、血栓形成を防ぎ血流を改善する薬です。過去に流産された時、あるいは死産された時に、子宮内容物病理標本、胎盤病理標本で血流の悪い所見があった場合にこの薬を使います。また、抗リン脂質抗体陽性で、胎盤で血流が悪くなることが予測された場合にも使います。
私が大阪府立母子保健総合医療センター母性内科に在職中、抗リン脂質抗体症候群の中でも最も赤ちゃんの予後が悪い、ループスアンチコアグラント陽性の患者さんにオルガランを使い、未分画ヘパリン、低分子ヘパリンと同等の効果を認め元気な赤ちゃんの誕生に寄与した薬です。一般的には、DIC(播種性血管内凝固症候群)という全身に血栓を起こす病気に最近使われ始めた薬で、DICにのみ保険適応となっています。
これまではDICにはヘパリンが使われていましたが、ヘパリンはいろいろの副作用があります。出血傾向、ヘパリン関連血小板減少、骨粗鬆症などです。オルガランはこれらの副作用がほとんどありません。また胎盤を通過しませんので、胎児にも影響しません。現在では、不育症に対して大学病院レベルで、各地で使われ始めています。
2 抗SS-A抗体による胎児完全房室ブロックを防ぐ試み
a.抗SS-A抗体とは
1969年ClarkがSLE(全身性エリテマトーデス)患者血液中に抗Ro抗体を発見、のちに1975年AlspaughとTanがSjogren syndrome(SS) の患者血液中に見出した抗体と同一であることがわかり、抗SS-A抗体と名付けました。この抗体はSjogren syndrome(シェーグレン症候群)の患者さんに高率に存在しますが、SLEなどの他の自己免疫疾患にも検出されます。近年、この抗体が妊娠中の母親に存在すると、胎児の心臓に完全房室ブロックを発症させるという報告がなされるようになりました。
胎児完全房室ブロックが発症すると徐脈となり、心不全、胎児水腫を引き起こし救命できたとしても胎児は、ペースメーカーの助けなくしては生きてゆけないのです。
b.母親への副腎皮質ホルモン治療の試み
胎児完全房室ブロックは、母親の持つ抗SS-A抗体が胎盤を通過して、胎児の心臓の刺激伝導路に炎症を引き起こし、心房から心室への電気刺激を遮断することで発症することがわかっています。当クリニックでは、胎児完全房室ブロックの児を出生した母親が次の妊娠をした場合、妊娠中に副腎皮質ホルモン治療を行っています。現在では、胎児完全房室ブロックの胎児を出生した母親だけでなく、抗SS-A抗体の高い値を持った母親にも同様の治療を行っています。その結果、副腎皮質ホルモン治療を受けた母親からはこれまで胎児完全房室ブロックの児は生まれていません。
これまでは胎児に完全房室ブロックが発症してから治療を行うという報告はありましたが、先天性胎児完全房室ブロックの胎児を生む可能性のある母体に妊娠初期から副腎皮質ホルモンを投与して、予防するという治療は世界で初めてのものであります。
c.どんな種類の副腎皮質ホルモンを何週から使用するか
副腎皮質ホルモンにもいろいろな種類があります。初めはプレドニゾロンを使用していましたが、β-メサゾンに変更、最近では再びプレドニゾロンを処方しています。これには次の理由があるからです。プレドニゾロンは妊婦に投与したとき胎盤の酵素で不活化され、ほとんど胎児に移行しません。一方β-メサゾンは不活化の程度が少ないことが知られています。治療の対象は胎児心臓の刺激伝導路での炎症ですので、胎盤移行の多いβ-メサゾンを選んで使用していました。
ただし、子宮内胎児発育不全の原因ともなりうるので、最近では少量のプレドニゾロンを妊娠12週から開始しています。プレドニゾロンによる胎児への催奇形性は、今では否定されていますが、胎児の器官形成期を避けるようにしています。胎児完全房室ブロックは、早く発症するものは妊娠20週前後で起こってきますが、妊娠12週からの薬物投与で遅くはないと考えています。
d.妊婦への副腎皮質ホルモン治療の結果
過去に胎児完全房室ブロックの胎児を出生した母親からも、また抗SS-A抗体が高値でこのような胎児を出生する可能性のある母親からも、副腎皮質ホルモン治療を行った症例には、ブロックは発症していません。ただし、副腎皮質ホルモンのうちβ-メサゾンを使用した症例から生まれた胎児は、子宮内胎児発育不全の傾向が強く出ました。
e.妊婦への副腎皮質ホルモン治療の功罪
胎児完全房室ブロックの胎児が、発生しなかったことは、確かにこの治療の効果だと考えられます。しかし、子宮内胎児発育不全の傾向が強く出たことは、副腎皮質ホルモン治療の胎児に対する副作用であり、とくに胎盤通過しやすく、胎児にそのほとんどが移行するβ-メサゾンで、この傾向が強く出ていることは、この薬剤の副作用であると考えるべきです。
β-メサゾンは、産科領域では切迫早産の際に、これまで多くの施設で頻用されている薬剤で、胎児の肺成熟を促す目的で使用されており、胎児が早産になった時に呼吸障害が起こらないようにするためのものです。1週間に12mgを2回筋肉注射します。このため胎児に対する副作用はいろいろな報告があります。胎児心臓の動脈管閉鎖、羊水減少などです。これらの副作用は切迫早産に対して妊娠中期から後期に使用される場合であり、胎児完全房室ブロックを防ぐべく妊娠12週から使用する場合は、子宮内胎児発育不全や胎児副腎機能抑制なども念頭に置かねばなりません。
母親に対しても副腎皮質ホルモン治療は副作用をもたらします。免疫力の低下によって感染を受けやすく、妊娠糖尿病の発症を起こす可能性があります。
おわりに
ここでは、母親がもつ自己抗体(抗SS-A抗体とループスアンチコアグラント)によって妊娠中に危険にさらされている胎児を、いかにして守っているかということを述べました。つまり、母体に薬剤を投与することによって子宮内環境を改善し、健全な胎児の出生をはかる、ある意味での胎児治療についてです。現代では子供を診る小児科、大人を診る内科とありますが、近い将来必ず胎児科が誕生すると確信しています。人間の始まりである胎児期を抜きにしてそのヒトの一生は語れない日が来るかもしれません。